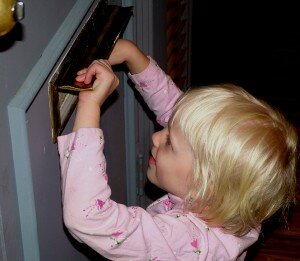心理ハック
書籍紹介『心理学を変えた40の研究』
本書の大きな長所は二つ。
- 心理学実験を中心に構成しているところ
- 主要な心理実験を多くカバーしているところ
この二点だ。
なぜこの2点がいいかというと、第1の、心理実験中心だから、少なくとも実験結果については嘘がない。嘘がないというのは言い過ぎでも、推測や解釈を積み重ねている本に比べれば、とにかく実験結果を踏まえて読むことができるというのは、安心できる。本書はこの意味で、親切だ。
第2に、とはいえ、現在の心理学は実験と論文が山積みされているので、その中に分け入っていくのは現実的ではない。主要な実験が40もカバーされていれば、それだけでも助かるというものだ。人間心理に興味があれば、もちろん面白い。
40というとかなり多いようだが(あるいはかなり少ないと見る向きもあるだろう。そこはバックグラウンドが何かでかなり違う)、いずれも全く「初耳だ」という人は、たぶん少ないと思う。詳しくは知らずとも「パブロフの犬」や「ハトに青信号をつつかせた実験」は、聞いたことがあると思う。また、「罰として人に電気ショッックを与えさせる実験」も、知っている人がたくさんいるはずだ。
一般書籍としては、こうした実験について、かなり細かく紹介されているし、まずは実験結果を、次いで解釈を、それから実験への批判にページを割くという構成は、わかりやすいし、期待に応えている。さらに、その後の展開と参考文献まで用意されている。有用で、勉強になるし、心強い。
最後までお読みになった読者で、心理学が専攻でない人は、一つの大きな物足りなさを感じるかもしれない。本書には、たくさんの興味深い心理実験が羅列されている。羅列されているだけ、といった印象すら受けるはずだ。人間は、これこれの条件下ではこう振る舞う。ストレスを感じるのは、こんなときだ。ネズミの学習過程はこうだが、これは人間にも十分当てはまりそうだ。などなど。さて…。
このように「人間心理アラカルト」が並んでいるというのに、そのアラカルトから導きだされるべき「人間心理の本質」とは何なのか。この本には書かれていない。なぜ?
つまりそれが心理学の現状というものなのだ。もちろんフロイトのように、がんばって「人間の心のモデル」を図解までしてくれた人もいる。けれども、そのアイデアの面白さと努力はそれとして、あれをあのまま信じている人は、今となっては少数派だ。
が、「フロイトの言うことはうさんくさい」という程度なら、心理学部に入学して1ヶ月の学生でも指摘できるけれど、フロイトモデルに替わる「心のモデル」を大胆にも提示して、それで博士号までとれたという人となると、「フロイトモデル」を信じている人と同じくらい少数派だ。
「40の研究」はこうした背景もあって、貴重だし面白い。まずは「事実」を収集しないといけない状況下では、頭に入れておくべき「事実」がまとまっているというのは、繰り返しになってしまうが必要不可欠なのだ。
「やる気」百景
百景は大げさですが、「やる気」と一口に言っても心理学的に、いろいろな捉え方があります。
たとえば、発達心理学で言えば、「子供の」モチベーションでしょうか。この場合、内発的、外発的動機付けという分け方がなされることがとても多く、「勉強」への「やる気」は、「成績」や「ご褒美」といった「外発的動機付け」と「好奇心の満足」という「内発的動機付け」というものに分けられます。後者がよい、とされますが、疑問の余地もあります。
行動心理学。ネズミがボタンを押すとチーズが出るという知見に基づく心理学では、心理学といいながら、「心」の存在を疑問視しています。とうぜん、「やる気」も目に見えるものでなくてはならず、「報酬」が「やる気」をほぼ決定づけます。チーズがたくさん出ると、やる気が出ることになるわけです。
このほとんど正反対といっていいのが、「深層心理学」。といいながら、両者には似たところもあるのですが、そうは言っても「深層心理学」には「心」があるのはもちろん、その「深層」まであるわけですから、「行動心理」とは究極的には矛盾します。「深層心理」には、「精神力学」という概念があって、心の「深層」には、「ドライブ」があります。「衝動」が「衝き動かす」。これが「やる気」の源と考えられます。
その他、人間中心主義などでは、マスローの欲求階層説があったり、社会心理学には承認欲求があったり、大脳生理学的には血糖値の低下が衝動の根源におかれたりと、実にいろいろな視点があって、展開がみられます。面白いと言えば面白いのですが、「要するに、心理学的に言って、やる気って何?」という問いにたいしては、心理学の中の立場によって、答えに特定の傾向が見られるわけです。
つまり、どのような「心理観」を持っているかによって、どうしても、素直に採用できる物の見方に違いが現れるわけです。もっともこれは、心理学に限った話では全くありません。
こういう風に考えてみますと、「やる気」について、改めて別建でモデルを構築しても、良さそうな気がしてきます。「チーズが出るからレバーを倒す」というのは、目に見えて明らかなので、これは否定のしようもありませんし、「好奇心故に勉強する」ということだって、当然あると思います。
それぞれの「善し悪し」よりも、それぞれのモチベーションについて、どんな条件下で、どのように働き、どんな場合には失われやすいかがわかるような、統一モデルを求めたいということです。その際、モチベーションの論拠として、脳や、神経、生理を探るのも、自然でしょう。
投稿しない、チェックしない
最近、少しずつ効果を上げてきたこととして、ちょっと厄介な仕事を始める直前に、決まってメールチェック、mixiチェック、twitterチェック等々を、しないようになりました。
そういうことをすること自体は、全然悪いことだと思わないのですが、「ちょっと厄介な仕事をする直前』にそれらをするのはよいことではないと、以前からたびたび感じてきました。
たぶん人間というのは、社会的動物であるために、ある種の人恋しさ、というのがウェットすぎるなら、社会的交歓欲求というものが不満な状態にあるのだと思います。
しかしそうした欲求は、あるのは当然としても、メールをチェックしたからといって、必ず満たされるものではありません。というよりもどちらかといえば、満たされないままに残ってしまうことの方が、体験的には多いのです。
なら、仕事をした方がマシ、という程度では、この習癖は押さえがたいため、基本的に「投稿しない」ことから始めています。自分が投稿しないのに、人が自分に投稿してくれる。そんなふうに考えるのは、うぬぼれもいいところだと思います。(少なくとも私については)。投稿しない以上、人が自分を気にかけてくれると期待するべき理由などなく、チェックしても空だと割り切ることもができます。
人とつながるのは、仕事が終わってからということで。