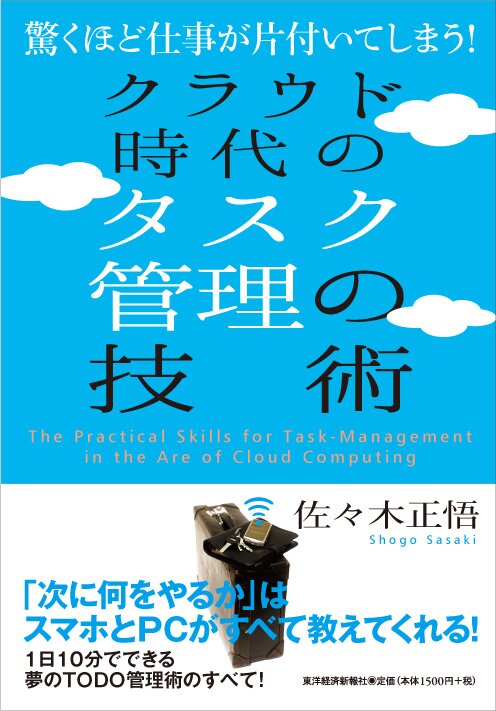心理ハック
080 ビジネス書作家のライフハック- 幻想と葛藤
097 ビジネス書作家のライフハック- 幻想と葛藤
欲しい。かなり欲しい。
いやいやもちろん分かっている。これは幻想なのだ。便利そうではあるが、絶対必要とは言えない。
これでブログを書ければとか、そんな事はいくらでも出てきそうだが、どうして出先でブログを書く必要があるか。家で書いている方がずっと効率的だ。私の場合。
私はもともと、出先でまでタイプしなければならないほど、忙しい物書きではない。出先では一種の興奮状態が起こるから、そこで仕事をした方が効率的だと思われがちだ。でも実際にはそうではなかった。タスクシュートで計測したらそのことが顕著だった。
▼続きはあすなろで
097 ビジネス書作家のライフハック- 幻想と葛藤 | | 作家の作業日報 | あすなろBLOG
079 ルーチンタスクも書き入れる
一般的なタスクリストというものには、いかにもそれらしいタスクばかりが並んでいて、いつもやっているはずのことがまったく書き込まれていません。わかりやすいところでは「休憩」がありません。
2時間ぶっ通しで仕事を進めるのは、あまり効率的ではありません。3つの大きなタスクがあるなら、せめて1回5分の休憩を2回挟みたいところです。これを入れて表を描き直してみると、次のようになります。
タスク名 見積もり時間(分)
銀行振込 30
休憩 5
プレゼン資料作成 60
休憩 5
税務資料チェック 30
総時間 130
例えばこのリストに取りかかったタイミングが午前10時であれば、午前中の業務は2時間を10分オーバーするか、最後の税務資料チェックには20分しかかけられなくなることが分かります。
実際には「午前中毎日やっていること」は休憩だけではないはずです。掃除や食事やパソコンのメンテナンスなど、私達には繰り返し発生する避けられない作業をいくつも抱えているのです。
これをルーチンタスクととらえ、拙著ではかなり重視しています。第4章では、毎日繰り返すルーチンタスク、毎週繰り返すルーチンタスク、毎月繰り返すルーチンタスク、特定日に繰り返すルーチンタスクをまとめて解説します。
このようなルーチンタスクは「カレンダー」に書き込んでいる方もいらっしゃるでしょうが、どこに書いてあっても実際には業務の中でこなさなければならないのですから、ルーチンタスクもきちんとタスクリストに書き入れて時間を見積もる必要があるのです。
ちなみに私は最も短く見積もっても、ルーチンタスクだけで4時間30分を毎日使っています。この中にはトイレ休憩や食事時間も含まれますが、そういうものも含んでいるだけに、絶対にこれ以上短くできないのです。
もしあなたの業務時間が1日9時間だとして、私の3倍食事を早く済ませ、トイレをギリギリまで我慢するとしても、ルーチン作業だけでおそらく2時間は失われるはずです。するとルーチン以外の業務には7時間しか注ぎ込めないのです。
この、「黙っていても失われる」「何をしている意識とは関係なく失われる」時間をゼロにすることは不可能です。タスクリストなど作らず、大事なことだけに没頭した方が効果が上がる、というような意見を述べる人は、この「黙っていても失われる時間」のことを念頭に置いていません。
大事なことに注ぎ込める最大の時間というものは、すでに決まっています。それはほとんどの人にとって「意外なほど」短いのです。意外なのは過大評価しているからに他なりません。
078 ビジネス書作家のライフハック- わかりやすい文章を書くための基本的なコツ
基本中の基本なのだが、コツは「ターゲットを決めること」だ。非常に簡単なようで、実に難しい。プロならプロなりに難しく、趣味で書くなら趣味で書くなりに難しく、その狭間のようなものにとっても難しい。
誰が読むのかを決めるということは、それ以外の人たちを切り捨てることになる。しかしプロの物書きというのは、読者が多ければ多いほど収入が多くなる道理なので、「出来れば誰も切り捨てたくない」という欲望にふりまわされる。
その方が自分に優しくなれるような気がするし、しかも収入も増えるとあって、一人でも多くの人を取り込みたくなって、文章がまずくなるのである。
▼続きはあすなろで
096 ビジネス書作家のライフハック- わかりやすい文章を書くための基本的なコツ | | 作家の作業日報 | あすなろBLOG
077 「簡単なタスクリスト」から発生する問題
拙著の「タスク管理システム」はけっこう大がかりかつ複雑に見えるため、今はまだそういうご批判をいただいていませんが、じきに「冷蔵庫にホワイトボードとマグネットをつければこんな大げさなもの要らないのに」というご批判をいただくことになるでしょう。
しかし、そうした簡単なリストだけではすぐに困った事態に見舞われるでしょう。次のような問題に突き当たる可能性があるからです。
タスクに手がけるべきタイミングとは「今が最善」という確信のあるとき
昨日あげたエントリの冒頭には
□ 銀行振込 30分
というタスクがありましたが、これはすぐできるタスクでしょうか? あるいは今すぐするべきタスクでしょうか? 午前中に銀行振込に「出かける」のは賢明ではないかもしれないし、得策でもないかもしれません。行く気にならないかもしれません。これが「先送り問題」です。
「先送り」はつねに悪いことではありません。今すぐするよりもあとでやった方がモチベーションが高まり、また時間の節約にもなるならむしろ先送りすべきです。
しかし問題は、「先に送った日時」です。
その時間帯は「あいている」のでしょうか? 会議があったり大きなプロジェクトの〆切が迫っている日に「銀行振込」を先送りすると、その日にもう一度先送りする羽目になります。
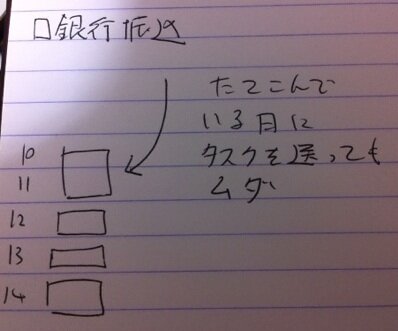
ですから「先送り」するためには送りたい日の状況が正確に見えていないといけないわけです。送りたい日の状況は正確に見えていますか? 未来の日の状況がまるで見えていないようなら、見えるようなシステムを構築しなければいけません。
そのようなシステムを構築する方法を説明したのが拙著なのです。
またたとえ先送りする時間があいていたとしても、先送りによって他に大きな影響が及ぶようではまずいでしょう。
たとえば、銀行振込というタスクの下にプレゼン資料作成というタスクがあった場合、その作業には60分という長い時間が見積もられていたりすると、すぐに取りかかる気持ちになれないかもしれません。
そのような場合またしても、「あとで取りかかる」ことにしてもいいわけですが、このタスクが他のプロジェクトのサブタスクであるような場合、「すぐやらないと他の業務が滞る」かもしれません。
この問題は当然、プロジェクト全体の〆切という問題とも関係してきます。すなわちプロジェクトごとの予定がパッと見えるようになっていないと、「今すぐやるべきか」「少し後に回せるか」の判断も出来ません。
少し経験のある人であれば、「たいていは今すぐやるのでまず間違いはない」というでしょうが、プロジェクトを5つ抱えていて、その5つのプロジェクト全部について「たいていは今すぐやるのでまず間違いはない」のでは困ります。事実はそうであっても、5つ同時に今すぐ取りかかることは出来ないからです。
したがって「今すぐ何かに取りかかる」ためにはどうしても、ある程度先の状況を手元で明らかに出来るということが必要なのです。これはまず冷蔵庫のホワイトボードではムリです。ある程度は構造的でしっかりとしたシステムがどうしても必要になるわけです。
076 タスクリストはなぜ片づかないか?
拙著は要するに「タスクリストにタスクを書いても片づかない」という問題を何とかするために書いた本です。ある意味テーマはそれだけです。
全てのタスクの時間を見積もるのも、タスクの順番をあらかじめ決めておくのも、プロジェクト名を徹底して統一するのも、全部目的はタスクリストをゼロに出来るようになるためです。
その全部を一冊に詰め込んだために、それからいまひとつ見慣れぬ方法についても言及したために、一見難しそうな本に見えるかもしれませんが、一つ一つは単純な仕組みです。
これからしばらくこのブログでは、本書の「難しげな」部分を補足するためにエントリをアップしていきます。最初はよく取りざたされる「時間の見積もり」について書くことにしましょう。
まずはそもそも「慣れる」ために、「午前中だけ」タスクを管理してみましょう。入門編のようですが「午前中のタスク管理」は重要です。経済心理学者ダニエル・カーネマンの研究によれば、もっとも人が疲労感を感じない時間帯というのは、朝の10時から12時くらいまでだからです。もちろんこれは夜寝て朝起きる人の話ですが。
疲労感が最も少ない時間帯をどう使うかは、仕事をする人にとって大切なことでしょう。夕方のだいぶ疲れがたまってきた時間帯に「息抜きに情報収集」するのと、朝早くから「気晴らしにネットブラウジングする」のとではまったく意味が違います。
タスクごとに時間を見積もる
というわけで午前中の10時から12時までの2時間に、どのタスクを片付けてしまうかを管理します。その具体的なやり方を紹介します。
まず、やるべきすべてのタスクを洗い出します。
この過程は決して頭の中だけでやらないようにしましょう。頭だけでやると、重複するタスクに気がつかなかったり、やるべきタスクを洗い出せなかったりします。なにより、頭の中だけでやるというのは、余計に疲れる結果になります。そのような余計な精神力を使わないために、タスク管理システムを利用するわけです。
紙に書き出すというのも、できれば避けましょう。紙に書き出すと、全部でどのくらいの時間がかかるかを計算しなければならなくなります。この書き出し作業にはエクセルか、Googleのスプレッドシートを使いましょう。
タスク名 見積もり時間(分)
銀行振込 30
プレゼン資料作成 60
税務資料チェック 30
総時間 120
私はセミナーなどで実際にこのようなリストを参加者の方に作っていただくことがあります。そうすると少なからぬ方が「120分でできることが少なすぎる」ことに驚くのです。
人は120分(2時間)という時間を過大に評価しています。すべての人がとはいいませんが、多くの人は過大評価しています。2時間あれば相当のことができるような気がするものです。8時間あればましてやです。だからこそ1日一生懸命働いて、「今日はあまりはかどらなかったなあ」などと感じるとがっかりします。でも「8時間あればかなりのことができる」と感じること自体が誤解なのです。
しかし心配はいりません。タスクにかかった時間を記録する習慣を3日間でも続ければ、「60分あればどのくらいのことができるのか?」がすぐに的確に分かるようになります。
多くの方はそのようなことを正確に記録したことがないので、「タスクにかかる時間を正確に見積もる」ということを最初からあきらめてしまっています。あきらめずにわずか3日記録を続けてみるだけでも、タスクにかかる時間が見積もれるようになって、その便利さに驚くでしょう。なぜなら同じ人間が似たような仕事に費やす時間は、それほど変化しないからです。
なお、タスクごとに見積もり時間情報を記入し、それを全部足し合わせるというのは、手でやってもいいのですが項目が増えるととても面倒です。もちろんエクセルの関数を使うのもいいのですが、時間の総和を算出する方法などご存じない方も多いでしょう。
Taskchuteがまさにこの目的にぴったりのツールなのです。シゴタノ!の大橋悦夫さんが開発されたツールです。下記のURLから無料でダウンロードできますので、興味のある方はチェックしてみてください。
▼Taskchute
http://cyblog.jp/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1
ここまでをまとめますと、「タスクリストが片づかない」のは片づかないようなリストを作っているからです。タスクごとにかかる時間をある程度正確に見積もって全部を足すことで、「終わるか終わらないか」が事前にはっきりするようになります。ただそれだけのことです。
「気合いを入れれば終わる」とか「本気になれば終わる」とかそういった問題ではないわけです。