心理ハック
わくわくさせる〆切の効果を活用する
シゴタノ!の大橋悦夫さんはこれを「壁」と呼んでいますが、この効果をさらに前から強調していたのが、『「超」整理法』の野口悠紀雄さんです。
デッドラインは、やる気を高めます。ただ、デッドラインは、きついものです。やる気を高めるかもしれませんが、それは、「惛い情念」のようなものになりがちです。
野口悠紀雄さんや大橋さんは、「ライフハック的な人」なので、そのような「猛烈サラリーマン」的な方法を、少しでも「脱根性論的な工夫」で改善できないかと考えます。その中から出てきたのが「壁」という考え方なのです。
野口先生は大学教授なので、海外に学会に行ったりすることがあります。それが「壁」になるわけです。これは大きな〆切ですが、すごく楽しみな〆切でもあります。仕事が終わったら初恋の人とデートに行く、というようなものです。
こういう条件ですと、人の心理はいやが上にも盛り上がります。〆切を破ったら編集者にバットで殴られるというようなのとは、決定的にちがいます。
ただ、「壁」がデートほどポジティブであることは、相当にラッキーです。いつもいつもそれほどのラッキーに恵まれるわけにはいきません。そこで大橋さんが考えたのは、人為的に「楽しみな壁」を作り出そうということでした。こういう発想は私にはライフハック的な精神に思えます。
問題はどうやって作り出すかということです。タスクシュートのコンテクストが9:00−12:00。12:00−15:00。15:00−18:00。となっているのは、このことと関係があるのです。
12:00は「昼食」です。「昼食」が楽しみであれば、これがポジティブな壁になる。18:00は「夕食」。フリーランスだからできることですが、これが楽しみな壁になる。
残るは15:00。おやつ? まあそれでもいいのですが、大橋さんは、私とスカイプチャット会議をここにもってくることに決めました。だからスカイプチャットは15:00スタートで、もう何年もそうなのです。
「壁」を楽しみにして3時間仕事をがんばる、というわけです。大橋さんは他にも、映画好きなので、仕事後に映画のチケットを予約しておくという方法を編み出していました。終わらないと映画が見られない。つまり、「壁」はポジティブであると同時に、ペナルティの効果も持つわけです。
さて、そろそろ日本対パラグアイです。私もこれを「壁」としてこの記事を急いで書き上げていたというわけです。この記事は予約投稿で、あげるのは一時間後の0:00になるはずですが。
読書は最大のストレスコーピング。であればこそ!
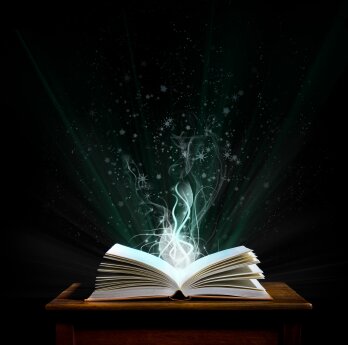
ちょっと古い記事になるのですが、「Reading ‘can help reduce stress’」という「研究結果」が発表されました。2009年5月の記事ですから、もう1年以上前のことですね。
Reading worked best, reducing stress levels by 68 per cent, said cognitive neuropsychologist Dr David Lewis.
Reading ‘can help reduce stress’
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
私はこの手の「研究結果」をあまり信用していません。「68%」などというのは、結局のところ何を意味しているのか? 「音楽より、散歩より」などといわれても、それぞれの効果は状況にはなはだ依存します。もちろん個人差も。
読む本はなんなのか? 聴く曲はなんなのか? 散歩といってもどこを歩くのか? 一人なのか? 人と一緒なのか? 疑問がつきないわけです。
ですが自分の「心理」に尋ねてみれば、「読書がストレスリダクションに役立つ」のは本当だと思います。ここで大事なのは、記事にもあるとおり、「どれほど没頭できるか?」「どれほど現実を忘れられるか?」です。
私もまた、「読書」は最大のストレスコーピングとして使ってきました。子供の頃からそうでした。「現実を忘れたい」からこそ「本の中に入る」のです。うまくいけば、読後1週間くらい、本の登場人物が、家族と同じくらい、頭から離れないほど「生きている」ことがあります。
こういうことにあまり埋没するのは、それなりに危険なところもあります。思春期の頃、そのことを意識するようになり、読書量を減らしました。
それはともかく、読書に「ストレスリダクション」の効果を求めるのであれば、「現実の役に立つ本」ばかり読むのは、どうかと思うのです。そうした本を読むことで「現実を忘れる」のは難しいことですから。
個人的には、最悪の場合でも、「実際の役に立つ本」を読むのは、全読書中の、50%にとどめておきたいところです。「なんの役にも立ちそうにない本」と「実際の役に立つ本」を読む比率は、1:1をもって限度としたい、ということです。
「実際の役に立つ本」ばかりを好んで読むということは、ともすれば、読書をストレスコーピングどころか、ストレスを増大させる元凶にしかねません。もっとも、このエントリの本当の意図からすると、そもそも読書についてこういう話をしていること自体、いけないことになるわけですが。(笑)
時間を見積もる目的には、少なくとも3つあります

タスクシュート方式でタスク管理するやり方には、いろいろな意見がありますが、中でも次の2つがほぼ決まって投げかけられる疑問です。
1 そもそもタスクの時間が正確に見積もれるはずがない
2 タスクの時間を全て見積もるのは、「縛られる」気がするのでやりたくない
1の意見に関しては、そもそも正確に見積もることが目的ではないとお答えし、2の意見に関しては、これは「タスクの時間を見積もること」を「スケジューリングすること」と混同しているとお答えします。
さらにもう一つ大事なことがあります。タスクの時間を見積もることの目的は、「どのくらい時間がかかるかを予測する」ことだけではないのです。実際には、3つの目的があります。
1.時間を確保する
ある種のアクションは、「時間を確保する」目的で、「予測時間」をタスクにセットします。たとえば「休憩」などについてはまさにこれです。
「佐々木さんは、休憩時間までも見積もるんですか?」と非常に怪訝そうに尋ねられる人もいますが、休憩時間は「確保する」のです。15分なら15分、無理をしてでも休みを取る。
これは、「見積もる」とか「予測する」という表現が正しくないのでしょうが、とりあえず「ちょっきり」になることが一番多いアクションです。なぜなら、「それだけの時間、やりたいから」それだけの時間を割り当てているのですから。
2.時間を見積もる
これが「時間の予測」です。つまり、「見積もる」というのは、3つの目的のうちの、1つなのです。
もちろん「正確に」なるとは限りません。「その通りに」できるとも限りません。「縛られる」というのも、少しちがいます。イヤなら、そしてそれですむなら、無視すればいいからです。
「見積もり」はシミュレーションの手段に過ぎません。これにこれだけかけて、それにそれだけかけて、それから休みをこれだけ入れたら、全部で何時間かかるのでしょうか? ということが分かれば、それでいいのです。
シミュレーションと結果が違うのは、当然あり得ることですし、「それでは仕事が回らない」というのも、何かが誤解されている気がします。「仕事が回らない」とすればそれは、シミュレーションをしたせいではないでしょう。
「予算を立てても、必要なモノを全て買うことができません」というのはおかしいでしょう。「ええ。それはお金が足りないか、必要なものが高すぎるのです」としか、答えようがありません。その場合、お金をもっと稼ぐか、必要経費をさらに切り詰めるか、どちらかしかないでしょう。
タスクにその話を当てはめるなら、仕事の速度をさらに上げるか、それともやることを減らすか、どちらかしかないでしょう。「予測」はあくまでも仮定的な結果を知るための手段であって、「予測した」からといって仕事がその通りに片付くことを保証するはずもなければ、強制するわけもありません。
3.時間で縛る
とは言え、「タスク時間の見積もり」が、行動を縛ることも、あります。これが「見積もる」ことの3つ目の目的です。
「最低でも15分くらいは、部屋の掃除に当てておいた方がいいでしょ」というわけです。これは1番目の「確保する」とよく似ていますが、「イヤでもこれだけはやる」という点で、正反対とも言えます。
1番目は、やりたくてもこれくらいにしておく、という意味でした。3番目は、イヤでもこれくらいはやる、ということです。
ここら辺に「縛られる」という感覚を、ことさらに抱かせる要素があるのでしょう。「私は自由を愛する人なので」という批判につながってくるわけです。
ただし、これもやはりちょっとした誤解なのです。別に「自由を愛する」でも全くOKなのです。これもお金にたとえるとわかりやすいと思いますが。
たとえば、家計をきっちり把握して、予算をしっかり立てたとしましょう。光熱費にはいくら、食費にはいくら、医療費にはいくら、税金にはいくら、保険にはいくら、そして貯金はいくらいくら、と。
しかし、そのまめまめしさにうんざりして「私は自由を愛する人なのでもうそんな予算など知ったことではない」というわけで、お菓子にほとんど全財産をつぎ込みました、ということでもいっこうにかまわないと思うのです。
ただ単に、私たちは「有り余るほどのお金」を持っていないので、「最低でも○○円くらいは、娘の教育費のために貯蓄し」て、「最大でも○○円程度に、Mac関連に費やす」ということにするわけです。
予算を立ててもただ単に、予め結果を家庭的に先取りすることしかできません。予算が何かを強制したり、お金を増やしたり、最適な結果を保証したりしてくれるはずがないのです。
スクリプトを止める

ジャッキをモチーフにした、昔ながらのジョークがあります。タイヤがパンクしたので、取り替えようとしたところ、ジャッキがないことに気づいた男が、ジャッキを借りるために隣家を訪れようとします。
しかし、道々男は勝手に想像してしまいます。「貸してくれなかったらどうしよう?」「もしかしたら居留守を使われるかもしれない」。そんな想像を巡らせるうちに、だんだん腹が立ってきます。
そして、隣家にたどり着いた時には、すっかり怒ってしまって、呼び出した相手をこう怒鳴りつけます。「頼まれたって、おまえのところのジャッキなんか、借りてやるものか!」
これにはいくつかバリエーションがあるのですが、基本は同じで、想像上の相手に勝手に腹を立ててしまう、男の滑稽さを笑っています。しかし、こんなにあからさまに滑稽な人は少ないでしょうが、多かれ少なかれ私たちはやってしまいがちな話なのです。
人は、想像上のストーリーに感動したり激高したりできる動物です。疑心暗鬼などというのは、全部これです。たとえば、夫婦喧嘩の真っ最中には、頭の中で罵りあうことが少なくありません。想像上のシミュレーションで、感情が高ぶってしまうわけです。
むろん、そういうシミュレーションが100%間違っているとは限りませんが、90%くらいは的外れです。なにより、実際にけんかする前に、想像の中でけんかするというのは、精神的には無意味な二重苦です。そのけんかを無制限に繰り返していれば、無間地獄です。
やっかいな問題。気持ちの高まりは「物語」によって簡単にエスカレートします。止めたいと思っても、止めるのはそう容易ではありません。
しかしこれは、「止めるべき」なのです。実際の対立はともかくも、空想の中で人を憎んでいて、いいことは何一つないのです。止めるためのマインドハックとして、「書き出す」「目の前のことに集中する」「大好きなことをやる」といったことはありますが、「止めよう」としなければ止まりません。
自分がジャッキの男のように「台本屋」になってしまったら、スクリプトを停止するよう努めてみましょう。1度でうまくいくことはまずありませんが、止めるように繰り返し努力すれば、やみます。そして10分も止められれば、そのときの気持ちよさに、驚くでしょう。
この、怒りの台本を止める快感を経験すればするほど、台本を止めるのは上手になります。それだけでも、自分の人生をコントロールできている幸福感が、幾ばくか手に入るはずです。
「考える時間」を別枠でとる
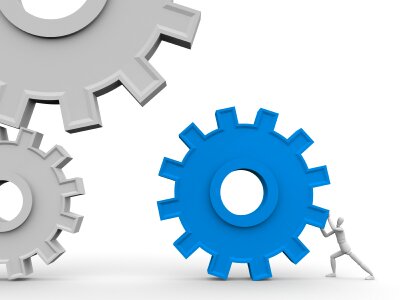
別に、「現代人は考える人が減った」とかなんとか、そういうことが言いたいわけではありません。
「先送り」してしまうとき、人は「考える時間」が取れなくなっていると思うのです。
先日、苦し紛れにあげた「人はずっと先送りしてきた問題を簡単に解決されるのは好まないのかもしれない」というエントリに予想以上の反響があって、ちょっと考えさせられました。
他人が、自分がずっと解決できずにいた問題を簡単に解決しようとしていると、自尊心が傷つくということはあるのでしょう。が、それよりもっとありそうだと思うことは、「その解決方法では納得できない」ということなのかもしれません。
「考えている」と人が言う時、実は、「悩んでいる」ことがしばしばです。
企画資料をまとめたり、本の原稿をあげたり、お風呂の掃除をしたりすることを先送りするのは、「面倒くさい」とか「もっと時間のある時にやりたい」とか、「そんなやり方じゃ先方に怒られる」とか言い分はありますが、よくきいてみると、「自分自身が納得できないやりかた」ではタスク処理する気になれないということが多いのです。
人はそれ程までに、自分自身を納得させたいのです。ただし、自分自身の説得には、結構時間がかかることがあります。しかも、「自分を納得させている」間は、仕事が全くはかどらないのです。
その時間は「考え中」となりますが、はためには(時には自分にも)ひどい無駄な事をしているように見える。これを俗に「グズグズしている」というのですが、本当はそう思ってはいけないのです。
本当は「考える時間」を取るべきです。もちろんそれは「ロジカル・シンキング」などと呼べるものではないにせよ、じつはタスクを前に進めるために欠かせない時間なのです。
この時間をずっととれずに、何となく先送りを繰り返して、そのうち他人が当たり前のように「解決」した時には、上述したとおり、「何となく納得がいかない」という気分が残るのでしょう。




