心理ハック
043 落ち込んで仕事にならないときに1つの対処法。「心の影」のことも書く

最近、いわゆるユングの「影」の概念について言及する機会を持ったので、エントリします。
不安定な価値観を持ち始めたとき不安定な影も生まれる
それまで「サプリメント」などにまったく興味を持っていなかったような人が、ある日突然「サプリメントに目覚めた!」と言うことがあります。おそらく健康上、何かとてもよいことがあったのでしょう。要因がサプリメントにあったかどうかはともかくとして。
この「要因がサプリメントにあったかどうかはともかく」という部分が「影」なのです。あるいは影になるのです。
盤石になっている価値観(すなわち頑迷とも言える)の影は濃く厄介な場合もありますが、日常では問題になりにくいものです。場合によっては「そんな価値観を自分が持っていると気づいてもいない」ほど本人にとって当然視されているからです。
しかし、冒頭のサプリメントのケースのように「最近新しく持ち始めた価値観」だと、本人にとっても「盤石になっていない」ため、これを盤石にする必要性を感じるのです。
インターネットはすばらしい、という価値観は、それがたとえ真実であってもほとんどの人にとって盤石にはなっていません。なぜならまだ歴史が新しいですから。こうした価値観は、その「影」に当たる、「インターネットなどくだらない」というアンチテーゼに対してまだもろいものです。
もろいゆえに「盤石のものとしたい」という人にしてみれば、「アンチテーゼを徹底的に叩かねばならない」という攻撃感情につながりやすいわけです。アンチテーゼである影は自分の心の中にあるわけです。しかしその影に力を与えるがごとき言説は、自分の外にあるかもしれません。これを攻撃したいと思えば、それが「投影」と呼ばれる心理機能です。
たとえば「タスクシュートで時間の見積もりをする仕事術は正しい」という価値観は、「トマトはうまい」という価値観に比べてまったくもろいものです。だからこそ自分の中にも「タスクシュートがいいなんて、本当だろうか?」という影につけいられやすく、「タスクシュートなんて役立たない」という言説にはムキになりがちなのです。「トマトはまずい」と言われても何とも感じないにもかかわらず。
書くことで価値観は安定する
ライティング・セラピー(筆記療法)と呼ばれる療法は、このような問題にもよく対処できます。インターネットはすばらしい、タスクシュートはすばらしい、Evernoteはすばらしいと思ったら、とりあえずそうしたことについて書くことです。
書いた事は頭の中だけの「記述」よりも安定します。忘れてしまったり「そうでもないかな」と思い直したりする確率が低くなるからです。
影による不安とは、忘れたりひっくり返ったりしてしまうことです。価値を報じているということは覚えておきたいということであり、覚えておきたいということは、逆の考えに「染まって」しまいたくないということです。
書き落とすことで、覚えておいたり価値観が逆転してしまう危険性が下がります。その分「影への不安」は減じられるでしょう。
あるいは書いて価値観を消滅させると「影」も消える
あるいはこうしたこともあります。「書いてみると、意外とそうでもない」と思うようになることもあるわけです。
報じている価値観そのものが消滅すれば、影も一緒に消え去ります。消滅させられないまでも、薄まるということはあります。
何でも「薄めれ」ばいいというものではありませんが、報じたばかりの価値観に異常に固執することには、あまり合理性が認められないケースは多々あります。書いて消滅するような価値であるなら、消滅させてしまった方が合理的と言ってもいいでしょう。
042 EvernoteのNotebookは書棚、タグは目次にする
私も含め「こんなに便利なものはない」というファンが多い一方、「何が便利なのかわからない」とも言われてしまうEvernote。それだけ広がってきたということで喜ばしいことでもありますが、個人が管理するにはデータが膨大になりすぎるきらいもあります。
「デジタルデータの整理」という話はどうしても評判が悪いと思わざるを得ませんが、でも私自身は整理してしまっていますので、その話をまとめておきます。
EvernoteのNotebookは「書棚」に見立てて整理する
簡便な二分法からはいります。Notebookは書棚に、タグは目次に見立ててしまうのです。この場合ノートはもちろん「本」です。
するとNotebookは「形式別」に分類することになります。書棚に本を並べる際、多くの人は形式別に並べているでしょう。ハードカバーはここ、辞書類はここ、コミックはここ、美術年鑑などはこっち、という具合です。
Notebookを3タイプに分類する
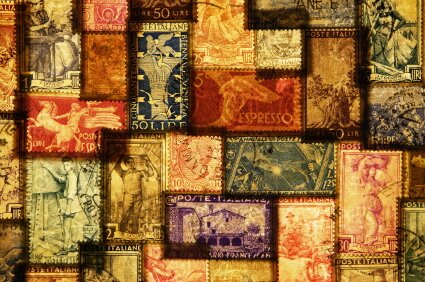
Evernoteにこのことを適用すると3種類の大きな形式を分けるのが大事になってくるように思います。
1 カタログリスト(ウィッシュリスト)
2 メモ・ノート・WEBクリップ
3 コレクション(ライフログなど)
書棚のアレゴリーを引きずっていますから、あえてそれらしい名前にしてありますが、名前はどうでもいいのです。123のいずれも、同じ形式のノートは同じNotebookに入れるという原則を守りつつ、扱いかたが違います。
1の「カタログリスト」は一見したところ3の「コレクション」と似た内容になるのですが、1で大事なのは1%程度。3で大事なのは100%という違いがあります。
1は並べておいたものの中から良さそうなものを選ぶためのリストであり、3は並べられたリストを堪能するためのリストです。
1も3も「タグ」はあまり必要ないのです。カタログやコレクションに「目次」が必ずしも必要ないようなものです。特にEvernoteであれば、並べると自動的に目次もできてしまいますから、たしかに不要なはずです。
1や3、特に3の「コレクション」にあえてタグ付けするなら「★」でしょう。コレクションはみな大事なものですが、中でも特に大事なコレクションがあるはずです。それにあえて「★」をつけるというような行為のために、タグは役に立ちます。
2はまったくちがいます。2のメモやノート、またはWEBクリップというものは、まとめたり編集したりすることによって「育てる」ためのものです。これは後ほどまとまった思想なり記事なりになるものです。それが人の役に立ったり未来の自分の役に立ったりするでしょう。
タグは目次
Notebookが「形式別」に整理するためのものだとすれば、タグは「内容別」に整理するためのものです。ノートを一冊の本にたとえるなら、本は「書棚のコーナー」に「入れられ」ますが、タグは「本の中」につけられるものです。
ただここがデジタルのいいところで、Evernoteのタグは外からも見えます。本の目次が本を開くまで見られないとはこの点でまったく異なります。だからいきなりタグから探すこともできます。物理的な本を目次から探すということは不可能です。
さらにキーワードサーチという方法まであります。これは進化した索引と言っていいと思いますが、これまた「すべての書籍の中から索引に該当する箇所だけ引っ張り出す」というデジタルならではのことがやれます。
タグにはもう一つ別の、目次的ではない使い方もありますが、それは別の機会に譲ります。
仕事に役立てる

Evernoteは生活を豊かにしてくれるすごいノートなのですが、仕事に徹底活用するなら、最初の方に戻って「1」のカタログと「3」のコレクションを「2」から完全に分離しきることです。
特に私のような職業のものにとって、真に役立つのは「2」のメモを育てることです。したがって「次に使用するメモ」と「現在使用中のメモ」が入っているノートブックのノート数を、ギリギリ少なくしておくことが大事になっています。
100ものメモを一週間で「育てる」ことなど私にはできないので、せいぜい3〜4のメモを厳選し、これをブログや連載のネタとし、ラフに変え、書き足していくわけです。
041 「思考」をメモがフォローする

しかし、これらを眺めるうちに一つ切り口が見えてきた。これに沿って整理を始めると、じつにスムーズに振り分けが進んだ。
上記引用はEvernoteのカテゴライズについて検討している内容です。こういうの「思考する」ということなのだろうと思います。
「ライフハック心理学」にうってつけのテーマでありながら極力私は「思考」というテーマを避けてきました。この語のイメージの幅広さと耳障りの良さは、無内容なテキストを増産させがちです。「思考のスピードを10倍にする」とでも言っておけば、あとは目の運動でも書いておけばよろしい。
記憶保持+記憶操作=思考
不完全ですが私はこういう定式を意識しています。思考とは、記憶保持と記憶操作です。ただ、目的が必要です。いつまで、なんのために記憶を保持し、操作するのか。
・異なる現実に対応するため
これまたやや不完全ながら、こんなふうに考えることにしています。異なる現実に対応するために、必要なアイデアを覚えておき、適当に操作する。
たとえばここに子供が7人いて、クッキーが30個あるというケース。子供が1人もおらず、ただ箱に30個のクッキーがはいっているというだけであれば、何も「思考する」必要はありません。好きなだけ自分が食べてもいいし、冷蔵庫にでもしまっておけばいいでしょう。
でも子供が7人登場したということになれば
30÷7=?
という式がとっさに浮かびます。現実が変わったからです。しかしこれは割り切れません。「4余り2」という回答を、覚えておく必要があります。造作もなく覚えておけたとしても、覚えていることにかわりはありません。
さらに「思考」を進めます。結局のところ7人全員に「平等に」配る必要があるとは限りません。大きいこと小さい子がいるかもしれませんし、30個丸々使い切る必要もないかもしれません。2人の子には5個ずつ、あとの子には4つずつにしてもいいでしょう。これをするには記憶保持と記憶操作が必要です。
しかし5個ずつと4つずつとなれば、「ずるいずるい」と言い出す子が現れるかもしれません。それに対して説得する準備もまた「思考」です。記憶内容の保持と、記憶操作があります。
余った2個は自分が食べるということもできます。これも記憶内容の保持と操作です。この思考内容を式でわざわざ示すとなれば
30−(7×4+1×2)=0
といった感じでしょうか。こうすると「答え」が「0になる」ことに重点を置いている印象になります。
どんな現実が欲しいのか
話を冒頭に戻します。
しかし、これらを眺めるうちに一つ切り口が見えてきた。これに沿って整理を始めると、じつにスムーズに振り分けが進んだ。
「眺めるうち」に進んでいるのが「思考」です。その真っ最中には、
・自分が扱うであろうメモやWEBクリップやメールなど様々なノートのイメージ(記憶保持)
・それらの区分の仕方によって見えて来るであろうリストのイメージ(記憶保持+操作)
・自分がEvernoteで見たいリスト(答え=今とは異なる現実)
についてめまぐるしく脳内の血流を巡らせているわけです。私の場合ではこういうことをやっていると身体にちょっとした緊張が走り、負担を覚えます。おそらく覚え切れそうもないほどの内容を記憶しようとして緊張するのです。
だからメモを使います。メモはこのケースでは記憶保持をフォローするものです。思考中にメモが必要になるのはこのためです。記憶の保持と操作の負担がだいぶ軽くなるのです。
040 有能な人がやる気を失いやすい理由

「自己効力感」という概念だけではなかなか見えてこないことがあります。「自分にはやれる・できる」という感覚が常に前向きな姿勢をもたらすとは限らないということです。
有能になれば批判能力も高くなる
人は能力を高めるほど、批判能力も高くなっていきます。これは仕方のないことです。
他人にこれを向ければ非常に感じが悪くなるに決まっていますが、自分自身にも常に向かってくるのです。スポーツを例に取ればわかりやすいでしょう。
五度の斜面でもしょっちゅう転んでいた子供でも、長年熱心に練習すれば、いつか三〇度でこぶだらけの斜面でモーグルできるようになります。
しかしそうなってしまうと、「ただ転ばずに三〇度の斜面を滑りきる」だけでは満足できなくなります。少し身体が遅れて後傾になったとか、切り替えが遅れて板がばらついたなど、高度な上に細かいことが気になり始めます。
この状態をしばらく続けるとまもなく「どうやっても満足できない」事態に見舞われます。自分自身の基準に照らした結果、高い水準を超えなければ不満だが、それ以上の水準を残すほどのやる気がわいてこなくなるのです。
先日NHKのテニス解説者が(御自身ももともともテニス選手だったわけですが)「クルム伊達さんを見ていると、自分ももう一度・・・と思いそうになることもあるけれど、彼女の練習風景を見ると、ここまでしなければいけないなら、自分はやりたくないなと正直思ってしまいます」と言っていました。そういうことです。
平均的なレベルの維持に切り替える
セルフ・ハンディキャッピングという心理学概念があります。私は有能な人がやる気を失っていく心理には、この概念が鍵を握っているとよく思うのです。
セルフハンディキャッピングself-handicapping
ある課題を遂行する際に,その遂行結果の評価的な意味をあいまいにするために,課題遂行の妨害となる障害を自ら作り出す行為。(中略)その課題遂行に失敗した場合には,失敗がその障害のためであると自己の能力の欠如に対する帰属が割り引きされ,成功した場合には,障害があったにもかかわらず成功したと自分の能力に対する帰属が割り増しされることを目的としている。(中略)
セルフハンディキャッピングとしては,アルコールの摂取,困難な状況の選択,努力の低下,また,不安や病気の主張などが指摘されている。自尊感情の維持のために,自ら失敗の可能性を高めたり自分の欠点を主張する,一見矛盾する行為として臨床的にも注目されている。
『有斐閣心理学事典』(太字は佐々木)
セルフ・ハンディキャップをかけることはなんとしても避けたいところです。人は「みっともない」という点をひどく気にかけるらしいのですが、そんなことより、最後の一節にあるとおり、これにはどこか「病的」なにおいがするからです。
セルフ・ハンディキャッピングが無意識に選択され、しかもしばしば「より好ましい、少なくとも十分理解されるべき」だと当人が感じているらしい点は、ますます要注目です。
その状況的な証拠として、人は他人のセルフ・ハンディキャップにひどく批判的であることがあげられます。同時に当人がしばしば「あえて困難な状況を選択した」などと主張するのには驚かされることがあります。
自分のセルフ・ハンディキャップは「誇るべきこと」と感じておきながら、他人のセルフ・ハンディキャップは批判する。無意識(無自覚)についての証拠を求めるのはたいてい不可能ですが、これはめずらしくいい線まで追い詰めているように見えます。
もともとの要因に立ち返ると、きつすぎる(自己)批判精神がありました。課題が困難だと感じていない限り「評価的な意味をあいまいにする」必要などありません。
困難な課題の克服の次に求めるものが、より困難な課題の克服だとするばかりでは、心が無気力を求め出すのもムリはないのです。課題に関する努力を一定以上費やし、ある程度の有能性を身につけたら、そこで自覚する必要があるわけです。
能力を自覚すれば、批判精神も無意識のうちに高まっていることが見えるわけです。ここから先は自己効力感ばかりではムリが出ます。高まった批判精神の取り扱いには注意が必要です。求める先を平均的なレベルの維持などに切り替えることが賢明でしょう。
そうすれば冒頭にあげたのっぽの△の頂点ばかりを意識して、無気力になったりアルコールに浸ったりせずにすむようになります。
039 いくら使ったら幸せになれるのか?

こういう問いかけ自体、なにかモラルめいた話になってしまいますが、そんな倫理的意味は一切ないものとして、単純な問い合わせとしてお考えください。
時間がいくらあれば、お金がいくらあれば、十分に充足できると思いますか?
私はこれをよく考えるのです。あくまで仮定として(現実に有り余るお金と無限の時間を持っていれば、このような自問自体しないはずです)ですが、今必要・欲しいものを買い切ることのできる総額とはいくらになって、それを完全に堪能するのに必要な時間とはどのくらいであるか、ということです。
タスクを放り込むin-boxが決まっているメリット
なぜここでいきなりタスクの話か。読み進んでいただければわかります。
何かをやりたいとか、やるべきだということになった時、それをすぐに記録しておくことのできる「容れ物」がいります。これがないと、処理しきれないほどタスクを抱えたり、やりきれないほどやりたいことが出てきた時、混乱の中で大事なことを忘れてしまいます。
1カ所にまとめることの利点は常識ですが
・そこに入れればなくならない
・そこを探せば必ず出てくる
・その中のものを比較検討できる
などのメリットがあるわけです。スーパーで買ってきたものをそのままにしておく人はめったにいないでしょう。冷蔵庫や棚の中にしまっていくのは、腐らせないという目的の他、次に自分が探す先に購入物を移動しておく必要があるからです。
レシピがあるメリット
タスクを入れるただ1つのin-boxが決まっているということは、それだけで意義のあることですが、やるべきことややりたいことをことごとく放り込んで、それだけで幸せになれるかといえば、なかなかそうもいきません。
1人の人間でも実際に行っている活動はたくさんあります。in-boxにただ放り込んでおいたのでは、「そこに大事なやるべきことの情報が集まっている」というだけで、それをいつまでにやるのか、どのようにやるのか、自分だけでやるのかといったことについて、何もわからなくなります。
実地に作業を進めるに当たって「レシピ」の力は強力です。手順、必要な資料などの情報、作業完遂にかかる時間などが整っていれば、タスクは高い確率で処理されるからです。
「レシピ」というのはシゴタノ!の大橋悦夫さんが一番よく使っている言葉で、「チェックリスト」の方が一般的でしょう。厳密に言うと「レシピ」は「チェックリスト」よりいささか広い概念です。
チェックリストは漏れなく作業を遂行するためのリストですが、レシピは手順、材料、所要時間などの情報まで集まっている1つの情報カードです。これがあってもなお「やる気がなくてできない」ことはありますが、やり方もあいまいで、気力ものってないとしても、レシピがあれば何とかなる。そういうことが少なくありません。
in-boxとレシピをつなぐもの
問題は「in-box」をどうやって「レシピ」の中に入れるかです。あるいは手持ちの「レシピ」にははいらないような真新しいアクションが発生するかも知れません。そうなると「レシピを作る」という作業が発生します。これはなかなか骨が折れ、しかも時間までかかります。
ここで、冒頭に戻るのです。わたしたちは「レシピ」がありさえすればやりたいことが全部できるわけではないのです。効率的に行動を取ることができ、時間も労力も節約はできますが、時間や体力、それにお金などのリソースには限界があります。
GTDはこの問題に対処するために、優先順位や鳥瞰的視点などの概念とともに、「いつかやるリスト」を用意しています。
私はこの問題に対応するために、時間的限界はタスクシュートを使って検討し、経済的限界は家計簿を使って検討しています。体力というリソースについてはうまく検討できていないのですが、睡眠時間で大ざっぱに代替えしています。
もちろん「やりたいこと」「読みたい本」「妻の要求」などは安定普遍の要素ではなく、かなり不安定です。この件については以前も書いた事ですが、「ライフログ」にはこの問題への新しい展開を期待できるかも知れません。
今「ライフハック」には「ライフログ」をより無理なく、より無意識に近い状況でも残せるという、古くて新しい役割を改めて強く意識したくなっています。



