心理ハック
記憶力と仕事術
「GTD実践者へのインタビュー」という記事が興味深かったので、それに関する話題をエントリーします。なお、このブログの著者であるヨシナさんとは、お会いしたことがあります。
GTD実践の前と後でどう変わった?
備忘録として機能して物忘れがなくなったという意見、これには同感です。仕事の主とする流れを忘れることはないと思いますが、ちょっとした雑用をやるタイミングを逃したりすることなくなったということですね。またいつやれば良い仕事かを判断つくようになったという意見、こちらも大いに同感です。目の前にぶら下がっている仕事を全て片付けようとすると、勤務時間内にはとても終わりません。GTDに仕事を預けることで将来やるべき仕事が明確になり安心して帰宅できる、もしくは今日やっておかないと納期に間に合わないなど、将来的な見通しがたつというメリットを感じることができます。
GTD実践者へのインタビュー
http://www.447blog.com/2010/05/gtd.html
全ては記憶してある?

GTDの話が出たりすると、「そんなことをしなくてもタスクは全て記憶できている」と言う人もいます。記憶力の個人差は非常に大きいので、全てを記憶でまかなえるという人も、現にいるでしょう。また、そもそもタスクが非常に少ない、という人もいるにちがいありません。
しかし、人の記憶に関する記憶には、バイアスがあるのです。「全部覚えている」と思っていても、それは「今覚えていることで全部だと思い込んでいるだけ」ということが少なくありません。
また、確かに全部覚えていても、それを的確に脳内操作できているかというと、そうでもなかったりします。「目の前にぶら下がっている仕事を全て片付けようとすると、勤務時間内にはとても終わりません」というのは、その一例です。これはただ覚えておけばいいという話とは違うのです。
88×36という計算は、24と48という数字をただ覚えておくだけでは、できません。記憶内容を操作しなければならないのです。この操作は、頭の中だけではできなくなることも多く、間違うことも多くなります。頭の外で操作する利点は、そこにあります。
利用可能性ヒューリスティック

人は、思い出しやすいことをもとに、記憶内容の利用を図るということを、「利用可能性ヒューリスティック」といいます。イスラエルの心理学者、トヴェルスキーとカーネマンが指摘したことです。
たとえば、「K」で始まる単語と、3番目の文字が「K」である単語のどちらが多いかと問われると、多くの人が「Kで始まる単語」と答えてしまいます。これは、「3番目がKの単語」など、思い出すのが面倒だからです。実際には、3番目が「K」の単語の方が、一般的な文章では2倍の頻度で登場します。
こういう記憶の性質から考えると、思い出しやすいタスクの方が手がけやすくなるのは当然です。そのような事態を未然に防ぐことも、仕事術を実践する目的のひとつでしょう。
先送りする心理
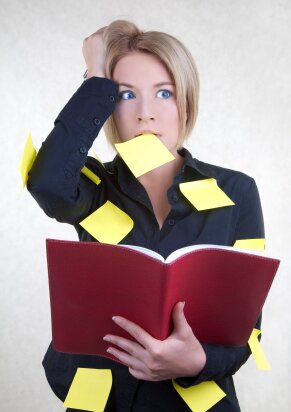
「先送りする」ということはたんに「あとでやることにする」のとイコールではありません。そんなことを言えば、「未来にやる予定を立てる」ことの全てが「先送り」になってしまいます。
先送りとは、「何かをやろうとしてできずにいる心理」をともなっています。「今すぐやった方がいい」「早めに手をつけるべきだ」と思いながら、全く手をつけられずにいるような心理状態を伴っているのです。
あらゆる物事について、そのような想いの呪縛にとらわれているとすれば、それは強迫性に近い状態ですが、そういう人は実際には少数です。たとえば「今全部食べてしまいたい! 朝食も昼食もおやつも夕食も!」という言葉を心理学のビデオで見たことがありますが、これは強迫的な人の言葉です。
もっと一般的な先送りの心理とは、「現在やるべきこと」にカテゴライズされるべきタスクが、「現在」に入りきらず、または「現在」の認知資源からあふれそうになっているが、それでもどうにか「現在」で処理しきってしまいたいという、二重拘束から生じています。
その結果、次のような心理状態に苦しむことになります。
「先送り」したいと思っていないのに時間を無駄にしてしまう
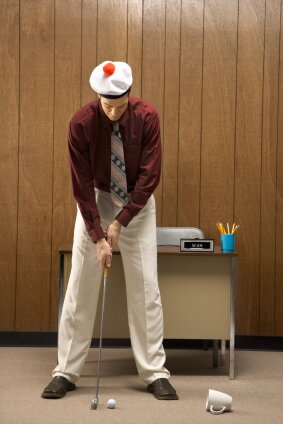
これはつまり「現在」に入りきらないか、もしくは「現在」やり終えてしまえる自信がないため、何もせずに時間を過ごしてしまっているわけです。
その結果ますます「現在」は縮小し、ますます事態が厳しくなっていくというスパイラルのなかにいます。
この心理状態は、「現在」を捨てるしかなくなるまで続くことが多々あります。
「先送り」するべきなのに、怖くて決断できない

その結果として迫られる「決断」はこうなります。もはや「現在」が十分でないなら、「先送りすべき」なのです。
もちろん、心理的には「今やるべきだ」という想い、つまり未練が残っているでしょう。それがなければ、「先送り」ではなく「未来の予定」になります。締め切りがないのなら、「いつかやりたいこと」になるかもしれません。
しかし、精神的なものであっても時間的なものであっても、あるいは金銭的なものであっても、キャパシティが足りなければ、決定するしかありません。つまり「今すぐはできない」ということを受け入れるしかないわけです。
これが受け入れられないのは、「イヤだから」です。つまり、「未来はバラ色であって欲しい」という正常な心理が働くため、「このイヤなタスク」が「明るい未来」を汚して欲しくないわけです。
理由も見通しもはっきりしないまま「先送り」してしまう

以上のような逡巡とは逆に、「明るい未来」の明るさに過剰の期待をかけてしまうやり方もあります。つまり、「明るい未来」に投げ入れてしまえば、「このイヤなタスク」も照らし出されて明るくなるような気がしてしまうのです。
これは余裕があるときや、過度に楽観的な人のやる「先送り」です。心のどこかには、「今やるべき」という気持ちがあるのですが、「明日やればいいだろう」と簡単に思うわけです。
これはまた、デッドラインがとても遠くにあるときに、あまりに早めに仕事に手がけようとすると、発生する心理でもあります。「今日やっても明日やっても大勢に影響がない」ため、「先送り」になり、それが毎日続くこともよくあります。
「現在やるべきこと」に集中できる環境を用意すること

あらゆるタスク管理システムの目指すところは、要するにここだと思います。「今やらなくてもいいことのことは頭から追い出し、今やるべきことは確実にアクセスできる」環境を用意することです。
したがって、現在見えるべきものだけを見えるようにすることと、見なくてもいいものは見えなくすることが、常に対になっているはずですし、そうできなくてはいけないでしょう。
「現在」というスパンが非常に短くなると、これが難しくなることは、あり得ます。しかし、それはまた別の問題です。ポイントは、自分が意識できる適切な「現在の長さ」(私の場合には2時間)をとらえ、その中で消費できる認知資源を確保しておくことです。
それ以上のタスクをそのスパンのなかでどうこうしようとしないことです。そうすれば「先送り」はほぼゼロになります。すなわち、「何かをやろうとしてできずにいる心理」とは無縁でいられるようになるということです。
ストレス神話 – Psychology Todayより

個人的に、信憑性がないのに広まってしまっている仮説のことを、「神話」と表現するのはいやなのですが、原文がそうなっているので、一応従っておきます。
Psychology Todayの「8つのストレス神話」の記事は、このブログでも前から取り上げたかったものだったので、5つめまでを簡単に紹介します。5つのなかでも重複があるほどなので、8つも必要ありません。
それでは、以下がPsychology Todayの言う「神話」-つまり、正しくないにもかかわらず、広く信じられている「俗説」です。
1.ストレスは環境に起因している
環境自体がストレスを生むわけではなく、環境からの刺激に関する「解釈」次第でストレスを受ける、ということです。だからこそ、同じ状況でも人によって、ストレスの受け方は全然違ってくるのです。
ハチがブンブンうなっていても、まるで気にしない人と、ものすごくストレスに感じる人がいるでしょう。
2.ストレスはモチベーションを高める
こういう考え方は幅広く信じられていますが、原文記事では、「よい刺激」と「ストレス」とは分けるべきだと言っています。
期限を設けたり、ゴールを設定することはよい刺激につながり、よい刺激は能力を高めてくれます。それに対して「心配」や「動揺」をもたらすストレスは、能力を発揮できなくさせるのです。
3.よいストレスもある
2と似た話ですが、これまた日本でもアメリカでもよく信じられています。もちろん、「よい刺激」のこともストレスと呼ぶ人からすると、こういうことになるのでしょう。
「ある程度のストレスは」という表現で始まります。しかしストレスは、心身に悪い影響を及ぼすことがほとんどなのです。
4.ストレス抜きの人生は生ぬるいものになってしまう
原文記事は面白い指摘をしています。「現代の多くの人は、ストレス抜きの人生というものを、もう想像もできなくなってしまっているのだ」というのです。
子供のころ、ストレスをほとんど感じていない、という時期はありませんでしたか? 子供の頃は、人生が生ぬるく、味気なかったでしょうか?
5.最善のストレス対処法は、運動、呼吸法、またはリラクセーションである
運動も呼吸法も、いいでしょう。しかし、1で述べてあるように、環境がストレスをもたらすわけではないのです。ストレスをもたらすのは、ある状況に関する、解釈なのです。
運動などによって一時的に、「ストレス因子を考えること」を忘れることはできるかもしれません。しかしそれは、ストレス因子をなくすわけではないのです。運動だけをストレス対処ツールとしていたのでは、解釈が戻ってきたとたん、ストレスも戻ってきてしまうでしょう。
むしろ、「解釈を忘れる」あるいは「解釈を変える」ことを重視すべきです。
▼原文はこちら
8 Deadly Myths About Stress
http://www.psychologytoday.com/blog/the-myth-stress/201005/8-deadly-myths-about-stress
忘れるということ

という小説があります。
全く売れた小説ではなく、もうだいぶ昔に絶版になってしまったのですが、個人的にはかなりのお気に入りです。
この小説は、いわゆる「認知の歪み」が知覚に影響するという現象を、物語化したものなのです。
主人公の女性は、物語のなかで、ある男性と恋に落ちますが、この二人の関係はいわゆる公には認められない類の関係です。
こういう話は小説には腐るほどありますが、恋に落ちる理由が面白いのです。ある特殊な館の「上の階の部屋」に入ったときにだけ、両者は恋愛関係にあることに、気づくのです。
両人は、「ふだんには、社会的約束事や、自分の運命に対する漠然としたあきらめのような感情」のせいで「心が曇っている」のですが、「館の上の階の部屋」を訪れたときだけ、「本当の自分たちに目覚める」ことができるので、「本当に一緒になるべきはこの相手だ」ということがわかるのです。
が、下に下りてしまうと、二人はそのことを自覚できなくなるので、再び両者の関係は、よそよそしく、つまらないものになります。
二人は何とかして、「上界での自覚」を「下に下りてからも維持したい」と思い、お互いにメモを交換したりしますが、なかなかうまくいきません。下に下りてしまうと、忘れてしまうのです。自分の名前や、自分たちがそれまで上界にいたということは覚えているのですが、最も重要なことは、忘れてしまうのです。
という設定の物語です。設定はぎこちなく、書きっぷりはいっそうぎこちないのですが、私はこの本でなくては味わえない感覚を思い出すので、時々読み返します。
多くの人は、たとえば海外旅行などで連泊したとき、時間感覚や、他人に対する意識の持ちようが、大きく変化した感じを味わった経験があると思います。そういうときには、自宅へ帰っても、同じように大きな気持ちで活動できたらいいのに、とは思うのですが、なかなかそうはいきません。
見慣れた玄関、見慣れた置き時計、見慣れたマウスなどなる空間に入ったとたん、何かがかちっと作動して、意識状態が元に戻るのです。そして、「あのときに感じたらしい大きな意識」は取り戻せなくなっています。
そういう意識の多重性を描いた小説なわけです。
「在宅勤務の落とし穴にはまらないための8つのカギ」をチェックしてみた

在宅勤務の落とし穴にはまらないための8つのカギという記事がおなじみの「Lifehacker」さんにあげられていたので、とりあえず自己チェック。
実はこうしたことをほとんど気にしない性格ですが、チェックリストになっていれば便利ですから、一応はやってみるのです。
一つ一つ見ていきますと。
1.スケジュール調整は前日夜にする
翌日の仕事を滞りなく進めるため、労働時間などの目標設定や方向付けをざっくりと行っておく。
私は前夜にやったり、朝にやったり、まちまちです。方向付けは決して「ざっくり」したものではなく、過剰なほど細かいくらいだと思いますが、夜やっても朝やっても大きな違いは生まないので、なるべく夜は早く寝るようにしています。
2.仕事に取り掛かる前に着替える
出勤するときのような服装に着替え、気持ちを切り替える。
これはやっていないです。着替えはしていますが。出勤するときのような服装に着替える、などということはないです。なぜそんなことをしなければならないのか?
3.朝食を食べる
朝食は食べています。はい。
4.タスクを体系化
15~20分刻みでタスクを分けるのが筆者流。
これは私の方がきっと体系化できているのではないかと密かに思います。
5.キッチンタイマーを活用
仕事開始前にタイマーをセットし、スイッチオン。仕事の集中力を高めてくれる。
キッチンタイマーは使わずに、Toodledoのタイマーを使っています。いずれにしてもタイマーを回しさえすれば、仕事が進むというものではないですが、点火プラグになってくれることもあるのは事実です。
6.小休憩も含めて一日をスケジューリング
スケジュール管理を行い、休憩時間も有意義に過ごす。しっかり休むだけでなく、洗濯物を畳んだり、食洗機から食器を取り出すなど家事をサポートする「生産的な休憩」を組み込んで、気持ちをリセットするも良し。
休憩は確かにスケジュールの中に入っていますが、「家事」と「休憩」は私にとって別のことです。「家事」「育児」「休憩」はそれぞれ別。娘の相手をする時間は休んでいることにならないような気がします。疲れます。
7.1日を2分割で働く
前半の仕事内容を振り返り、後半の作業に活かす。
これはとても大事だと思います。とりあえず、1日は8分割にしていますが、なんで分けるかといえば、心理状況が大きく変わるからです。
8.Webブラウジングを制限する
Firefoxのプロファイルを複数作成する。「仕事用」プロファイルを作り、プロファイルを切り替えることによってオンとオフを切り替える。
ここまではしていませんが、これも大事だと思います。私のやり方はありがちで、仕事をするときには、メールを閉じ、Twitterを閉じ、Facebookを閉じます。つまり、非SNSモードになります。



